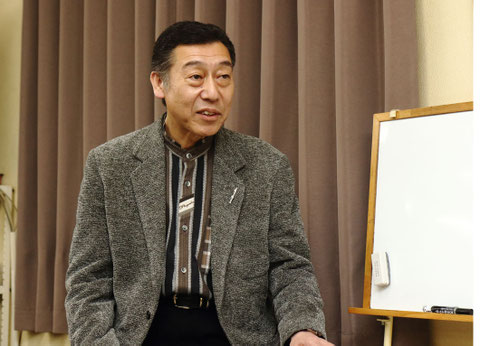- HOME
- Blog
- About BD
- お問合わせ
大橋清孝・JPBA53期生
プロ引退、そして復帰。ビリヤードに魅せられた半生
2020年4月
昨年(2019年)、
JPBA53期生としてプロ復帰を果たした
「ミスターローテーション」こと大橋清孝プロ。
歴の長いビリヤードファンにとっては
馴染みが深い名前である一方で、
新しいファンは「どんな人なの?」と
思うかもしれない。
大橋プロと話をしたことがある人ならば、
ビリヤードへのひたむきな愛情と
ビリヤードを愛する全ての人への
優しい眼差しを知っているだろう。
自由にビリヤードが楽しめない今だからこそ。
中断期間を経て今また撞球の道を往く
先輩とビリヤードを語りたい。
そんな思いで大橋プロに
インタビューにご登場いただいた
(※取材は3月中旬に滋賀で行いました)。
取材協力:早川工房 & SOUL WOOD(滋賀県)
…………
Kiyotaka Ohhashi
大橋清孝(おおはし・きよたか)
1958年3月5日生。大阪市出身・在住
10代のアマ時代から強豪ORC
(大阪ローテーションクラブ)のエース格として活躍。
『名人位』を一度防衛した後にプロ転向。
1990年『アジア選手権』準優勝や
2002年『アジア大会』(釜山)ビリヤード日本代表、
『西日本プロツアー』優勝多数など
優れた実績を挙げて2005年にプロ引退。
2019年にプロ復帰を果たした。
…………
ビリヤードへの想いが蘇ってきました
――今日はお忙しいところをありがとうございます。まずは2005年のプロ引退、そして昨年(2019年)の復帰について、簡単に経緯をお聞かせください。
大橋:私が2005年にJPBAを退会したのは、仕事に専念しなければならないという状況の中で決めたことでした。付き合いがあった会社の代表取締役という仕事を引き受けることになり、しかもそれが私自身が初めて経験する製造業だということもありました。他にも複数の会社経営に関わっていましたので、「中途半端はいけない」と思い、「もう一生キューを握らない」というくらいの覚悟で離れました。
――その後、全く撞く機会はなかったのですか?
大橋:はい、丸14年間全くと言って良い程キューを握っていません。離れて3年目に1回、5年目に1回か2回くらいハウスキューでちょっと転がしたくらいです。そして人に肩を押されてですが、仕事も落ち着いていましたので、「還暦を機にもう一度やってみよう」となった次第です。そうして始めてみたら、思ったより勘は鈍ってはいませんでしたが、やはり現役の頃のようにはいきませんでした。そして何もかもが変わっていて、もう浦島太郎状態でしたね(笑)。
――特に印象に残る点を教えてください。
大橋:まずラックシートを見て「何やこれは?」と(笑)。私が離れたのはスポットシール(小さなドーナツ状のシールをラシャに直接貼る形式)が普及し始めた頃でした。ラックシートが出来たことでゲームの展開も速くなっていますよね。そしてみんなが「ハイテクキュー、ハイテクキュー」と言っているけど、「ハイテクキューって何や?」と(笑)。それで興味が湧いて、やはりビリヤードへの想いが蘇ってきました。
――あふれるビリヤード愛を抑えきれなくなったのですね。
大橋:そういうことですね。もともとが命の次に大切なビリヤードでしたから。そうすると、プロという肩書きで試合にも出てみたくなりますし、「こんな年寄りでもやるんだぞ」と若い選手に刺激を与えることができたら、自分の存在価値もあるのではないかと。そして「大好きなビリヤードを仕事につなげられたらいいな」とも考えるようになりました。不登校やひきこもりの子供やシニアの生涯スポーツなど、ビリヤードの力で社会貢献ができるということは以前から考えていたことです。
――すると近い将来の展望として、ビリヤードを何らかの仕事として考えておられると?
大橋:そう考えていました。しかし、今はコロナウイルスの影響で世の中全体がそれどころではない状況になってしまっていますから、少し先の話にはなると思います。それでもビリヤードの素晴らしさや面白さには、社会に貢献できることがたくさんあると思っています。
ライバルは手球、敵は湿気
――道具に関する話を少し掘り下げて聞かせてください。
大橋:個人的に変化として大きいと感じるのはラックシートによってゲーム性が変わった点ですね。もちろんキューの性質についても、元々からキューが大好きですから、興味深く見ています。カーボンのシャフトは他のハイテクシャフトしかりですが、テニスラケットやゴルフクラブのようにスイートスポットが大きくなったと思います。この点はビリヤードの道具も他のスポーツに追いついてきたのだなと。私の好みかどうかは別としてですが(笑)。
――キューの性能変化に伴って撞点やプレースタイルにも変化が出てきたかと思いますが、大橋プロの見解はいかがでしょう?
大橋:私は「ライバルは?」と聞かれたら昔から「手球」、「撞点」と答えていたんですね。ちょっとキザですが(笑)。撞点は無数にあり、それを自分で選んでゲームを組み立てていくのがビリヤードのロマンですからね。シャフトの性能で確かに撞点に変化も出てきたと思いますが、それでも結局は球体の運動は理に叶った撞点を撞く以外はないので、個人的にはやるべきことは同じだと思っています。しかし最近は「ライバルは手球です」という前に課題がありますが。
――と言いますと?
大橋:還暦を超えてくると、自分自身をコントロールしてやることが課題になってきました。例えば目も悪くなって見えにくい球もあります。また体力的に続かない場面もあります。そんな時に自分自身を励ましたりなだめてみたりと、自分をケアしながらプレーするような感じですね(笑)。それでもビリヤードには挑戦心が必要で、やっぱり球撞きは面白い。今も愛してやまないのは変わりません。ちなみにライバルは手球、撞点ですが、「敵は?」と聞かれたら「湿気」と答えています。アマチュアであった40年程前に海外派遣に参加させてもらって厳しいコンディションを体験して以来、ビリヤードの最大の敵は湿気だと思っています。
――「ライバルは手球、敵は湿気」。大橋プロらしい名言ですね。さて、ミスターローテーションのニックネームを持つ大橋プロですが、やはりローテーションへの競技愛は変わりませんか?
大橋:うーん、最近のローテーションはゲーム性が変わりましてね。今は好きかというと少し微妙かもしれません。と言うのも、ルールやコンディションが変わって、9ボール化していると感じるからです。しかしローテーションのハイランは今も魅力的です。1キュー(イニング)でいかにこなすか? というのが醍醐味です。
――ハイランに挑戦する。それは確率や勝率と天秤にかける時もありますね。
大橋:3つ取ってセーフティ、3つ取ってセーフティ。こんな取り方でも成立するのが現代ビリヤードかもしれません。しかしネクストが危険であっても、挑戦すべき場面もあると私は思います。勝ち負けだけであれば、刻んでセーフティは正解だと思います。でも、そこにロマンが欲しいんですよ。ビリヤードにはストーリーがあるんです。これは言い換えればプランニングですね。例えば6番のトラブルに対して、3番でセーフティを仕掛けて4番で割りに行くのか、ギリギリの5番で割りに行くのか、プランの変更はあるとしても、1番の時点でそれを描いていること。これがストーリーですね。
――ストーリーとロマン。大橋プロは以前からそうおっしゃっていました。
大橋:240点を撞き切って一度も撞かさずに勝つのもひとつのストーリー。私も何度もやりました。もちろんされたこともありますけどね(笑)。そして守りであっても攻めのセーフティをしたい。今のジャンプキューで死守するセーフ(セーフするだけが目的)は大嫌いです。クッションとジャンプの選択に基準や想いがあればいいんですよ。ただ飛ばして当てるだけ、というのは好きになれないですね。
――とても大橋プロらしいコメントですね(笑)。
大橋:自分もジャンプキューを持っていますし、使いますよ。以前の現役の頃も持っていました。ただ成功しているうちはいいけど、ここ一番でジャンプキューを使って失敗した時のみじめさも痛感していますからね。まあ今のプレイヤーはみんなジャンプが上手です。空クッションなどプランの比較をして、その上でジャンプを選ぶのであれば私もそれはアリだと思います。
キューは良い悪いではなく個性・特性と捉える
――大橋プロといえばキューが大好きで大切にされることでも有名です。今現在、キューに何を求めておられますか?
大橋:キューは趣味嗜好の問題で、道具は体の一部。その点では服やネクタイと同じですね。まずは色や柄から。異性でもそうです。人によって好みのタイプは違いますよね。これは表現を間違えるとコンプライアンス的に引っかかってしまいますが(笑)。キューはデザインありきですが、もちろん性能も求めます。最近は縁があって早川工房のキューを使わせてもらっていて、ちょうど今、新しいデザインのキューを作ってもらっています。デザインも性能も仕上がりが楽しみですね。ちなみに早川さんを紹介してくれたナビゲーターのキューケースも愛用させてもらっています。
――キューの性能についてのお考えをお聞かせいただけますか?
大橋:キューの性能は突き詰めると、撞く技量や好みの問題になってくると思っています。「どんなキューが良いですか?」と聞かれたら、返答は「何を求めていくのか?」という確認になります。良い悪いではなく、個性・特性と捉えた方がよいですね。そしてキューは少しでも変化すると特性が変わります。たとえばテーパーを少し触ってやるだけでも球の反応や動きは変わりますし、ニスの塗りひとつでもしなりは変化します。タップひとつでもしかりです。
――なるほどです。ところで現在、キューは何本所有されていますか?
大橋:今は4本くらいです。プロを辞める時に、踏ん切りをつけるために持っていたキューはほぼ処分しましたので。以前は最も多い時だと12、3本くらい持っていたと思います。日本に入っていなかったキューを海外から取り寄せたりもしていましたね。
父親が自宅の2階でビリヤード場を開いたんです
――話は変わりますが、大橋プロがビリヤードと出会った頃のことを聞かせていただけますか?
大橋:僕がビリヤードを始めたのは11歳、小5の後半です。実家の祖父が瓦屋さんで、技術を高く評価される職人だったと聞いています。そして父が瓦屋を廃業して、喫茶店をしたりして、他の商売を考えていた時に自宅の2階にテーブルを2台置いたビリヤード場を開いたんです。ちなみに父親はビリヤードに関しては素人でした。
――小学生の時に家業として始めたビリヤードに興味を持たれたのですね?
大橋:当初はただ球体の運動が面白くてハマりましたね。中学1年の時にはボウラードで150点くらい出していました。当時はまだまだビリヤードのイメージも良くなかったので、母親が嫌がって「夜は店に来るな」と。でも中学2年くらいになると、よそから道場破りのような恰好で「誰か撞いてくれ」という人が来たら相手をすることはありました。
――50年近く前の話。まだ『ジュニア』という概念がない時ですよね?
大橋:全くなかったですね(笑)。母親が「中学の間は試合に出るのもダメだ」と。だから高校1年の4月に『大阪十六夜会』に初めて出場しました。そこで緊張はしましたが、確かベスト4に入りました。中学を卒業したばかりで坊主頭でしたから、周囲が「誰や?」とザワついていた記憶があります。会場は大阪の『高橋ボウル』で、参加者が140名だか150名だったとかで「過去最多出場数」だったと聞きました。
――今の時代であれば、SNSなどで「天才少年現る!」と話題になったことでしょう。
大橋:初めて出た試合で入賞できたので自分では火が点いたけど、実力的にはまだまだだったと思います。そして1ヶ月後の(5月16日)の十六夜会までの間に父親が脳溢血で倒れて急死しました。それで中学ではバスケットボールをしていたのですが、高校ではクラブ活動などは入らずに、店番をするようになりました。
――若くしてお父様を亡くされたのですね。しかしビリヤードに一層のめり込む流れであったのだろうと感じます。
大橋:結果としてそうなっていますね。当時、ORCは入会の資格を取らないと入れない決まりがありました。十六夜会は(大会規模が大きいので)優勝1回でいいのが、『三金会』(地域のマンスリー)はローカルなので2回優勝しないと入会の資格を得ることができませんでした。大阪ローテーションクラブと(いう正式名称)は知らなかったけど、ORCが強豪選手の集う会であるということは小学校の時には知っていました。高校生の時には自分自身も入りたいし、入会してもっと実力をつけたいと思っていました。
――伝統のクラブに高校生が入る。特に時代を考えると驚きしかありません。
大橋:父親が(ORCの重鎮であった)岡田実さんに「高校に入ったら頼むで」と言っていたんです。そして三金会に3度目の出場をした9月に優勝。さらに10月、11月と3連覇して、12月は準優勝だったと記憶しています。これにより権利を得てORCに入会しました。まあ高校1年といっても老け顔で生意気な顔していましたから(笑)。私のORCとしての活動はこうして昭和49年1月より始まりました。
――とても面白い話をありがとうございました。機会があれば、ぜひその後のアマチュア選手としてのご活躍ぶりや(1度目の)プロ入り辺りの話もぜひおうかがいしたいです。
大橋:こちらこそ昔の話をさせてもらって、懐かしい思い出が蘇りました。今はこんな状況ですが、ビリヤードは本当に奥が深くて素晴らしい競技です。新型コロナウイルスが収まった時には、ビリヤードをこれまで以上に愛して、そしてもっと楽しんでいただきたいと思います。
(了)